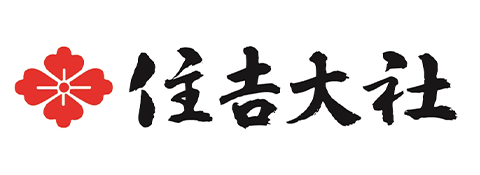導入前の課題
- モデル選定から運用開始までが複雑で難解だった
- 管理運用に手間がかかっていた
- 保証が短い、もしくは無かった
導入システム
- 本体:RackStation RS18017xs+
- JBOD:Expansion Unit RX1217sas ※本体1台+JBOD5台の構成
導入メリット
- 導入投資コストと業務効率の最適解
- 5年間の長期にわたるメーカー保証
- 10GbE標準搭載ストレージ

「自社内で管理まで行う作業用ドライブに求めたのは、管理の容易さと容量単価の安さ、映像処理に必要十分な可用性、そして処理速度の速さでした。その観点から当社はSynologyのNASを選定しました」
映像事業本部 プロダクション部 技術グループ
土屋 清晃氏

「高いお金を払えば、より高性能なストレージを手に入れることができます。我々が求めているのは、投資コストと安全性・業務効率の最適解です。今回の導入においてはSynologyのNASがその答えでした」
映像事業本部 チーフテクニカルディレクター
山田 堅二郎氏
日本を代表する映像加工の総合商社
株式会社IMAGICAは、国内最大のポストプロダクション。ポストプロダクションとは、映像・音声素材を編集・加工し、テレビや劇場映画、WEB動画など最終的な納品規格に合わせてコンテンツを仕上げていく過程の総称だ。1935年、IMAGICAの前身である極東現像所は、当時東洋のハリウッドと呼ばれた京都太秦の地に、フィルムの現像を行う日本で最初の商業ラボとして設立された。現在、劇場用映画やテレビ番組、CM等の仕上げで国内トップシェアを持つ同社の従業員は約1000名。そのうち半数以上を映像に関する技術者、技能者が占める。映像に関するあらゆる課題にワンストップで対応する企業は国内には例が無く、創業以来、日本の映像制作を下支えし続けている。

映像データ拡大を受け管理が容易なNASを採用
映像編集のデジタル化は過去4、5年の間に急速に進展した。劇場用映画を例にすると、現在、撮影にフィルムが使われることはほぼ無く、上映用プリントもほぼ100%デジタル化している。さらに解像度の上昇に伴い、取り扱うデータ量も飛躍的に増大している。劇場用映画のマスターデータ1作品あたりの容量は数テラバイトになり、編集段階ではその10~20倍以上のデータがストレージに蓄積されることになる。同社は、部門を越えて利用され、手厚い保守サービスを受けている「センターストレージ」と各作業者が一時保管に利用する「ニアラインストレージ」の2種類のストレージを使い分けることで、巨大化する映像データの効率的な運用を心掛けてきた。ニアラインストレージは容量単価の観点からリナックスOSでカスタムメイドしたNASを採用してきたが、管理に一定の専門知識が必要になるという課題が生じていた。
こうした課題の解決のため情報を収集する中で出会ったのが、SynologyのNAS製品だった。
「作業者がデータを一時保管するニアラインストレージには、センターストレージと比べ、容量単価の安さが強く求められます。その観点で当社が注目したのはSynology製品でした。まずは誰かが試してみようということになり、我々のグループが利用するニアラインストレージにSynology製品を導入してみることになりました」(土屋 清晃氏) 土屋氏はSynologyのダイレクトパートナーとして独自のインテグレーションサービスや保守サービスを提供するKSG 国際産業技術に提案を依頼。その提案を受け、新たなニアラインストレージとして同社が選択したのは、超高速ファイル転送を可能にする10GBase-Tポートを2つ備えるRackStation RS18017xs+と、5基の144TBの容量を持つJBODであるExpansion Unit RX1217sasの組み合わせだった。

10GbEの高速性は業務効率化にも有効
「従来のストレージと比較してまず評価したいのは、メーカー保証期間が標準で5年間となっていた点です。今後のデジタルデータ容量の拡大に伴うハードウェア陳腐化は避けることができません。そういう意味で5年間という保証期間はハードウェアに対する当社のスタンスにぴったりなものでした。もちろん、誰もが扱いやすいWeb GUIで管理できるNASがカスタムメイドなNASよりも安い容量単価で調達できることも魅力の一つです」(土屋 清晃氏)
山田氏の部署では、運用開始から1か月余りで、その使用容量が7割を超えたという。これは映像業界において、データ量が飛躍的に増大していることを示す数字と言えるだろう。
「近年、データが肥大化する中、コピー作業は大きな負担になっています。こうした中、標準で10GbEが搭載され、高速のファイル転送が可能になる点も魅力の一つです。それによる作業時間の短縮化は、当社の働き方改革にもつながるのではと期待しています」(山田 堅二郎氏)